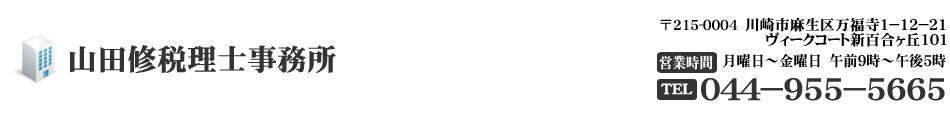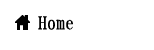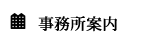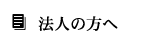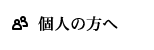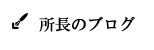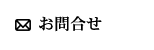個人の方へ
法人成り
個人事業主、節税改
事例研究
所得税税法上 もくろみ、慣行及び嗜好として負担した支出(家事関連費)と必要経費の範囲について
専有部分の形状、床面積等が契約時のそれと異なったことによる迷惑料の所得の区分
譲渡所得の計算上、相続により取得した借地権の瑕疵について支払った和解金及び弁護士費用について取得原価算入の可否
青色事業専従者の要件
専ら従事の意味と法人の役員は青色事業専従者になるか
事例
葛飾柴又帝釈天前の参道で団子の小売を営む甲は、その妻(通称おばちゃん)に青色事業専従者として年800万円の給与を支給している。
また、団子の製造は甲が代表取締役を務める株式会社「とらや」が販売とは別に行っており、おばちゃんに月額20万円の役員報酬を支給している。
問題点
青色事業専従者の「専ら従事」とはどのようなことをさすか。
法人役員の妻は青色事業専従者になり得るか?
回答
1. おばちゃんが名目もしくは非常勤役員である場合には、青色事業専従者に該当する。
ただし、法人税法上その報酬が適正であるかは別途検討する必要がある。
2. おばちゃんが常勤取締役である場合、青色事業専従者に該当せずその給与は
必要経費に算入できない。
思考過程
所得税法では、納税者と生計を一にする配偶者等の親族が当該事業に従事したことその他の事由により当該事業から給与、地代家賃等の支払を受けても必要経費に算入せず一方それらは当該親族の所得としない旨の規定がある。所得税法56条
これは所得を恣意的に家族に分散し税負担の回避を防止するためである。
ただし、その例外として青色申告の家族専従者について一定の要件のもとその者の労務の対価として相当と認められる金額を支払えばその全額が青色申告者の事業に係る必要経費に算入することを認めている。
所57条
青色申告の承認を受けている居住者と
生計を一にする配偶者その他の親族で
専らその居住者の営む事業に従事するものが
給与の支払を受けた場合
その給与の金額で
その労務に従事した期間
労務の性質及びその提供の程度
その事業の種類及び規模
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると認められるものは
必要経費に算入する。
政令で定める状況とは、
所得税法施行令第165条
《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定》
当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかによる。
専ら従事する期間に含まれないもの
(1) 学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事する者を除く。)
(2) 他に職業を有する者
(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
(3) 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
専ら従事とは 辞書によると そのことばかり、一途という意味
青色事業専従者に該当しない裁決判例は、
千葉地方裁判所平成22年2月26日判決
原告の営む事業の業種業態原告の妻である甲が従事している具体的業務内容やその業務量等に照らし甲が業務の一部を補助していた事実が認められるもののその程度は原告が行う同業務全体との比較からすれば少ない程度にとどまるものであり甲はむしろ専業主婦として家事等に主に従事していたとみるのが相当である 。
山口地方裁判所昭和58年3月17日判決
甲は主婦としての仕事の合間を縫って乙ビルに出向いていたもののその多くは他の会社の業務に従事し乙ビルの業務はさらにその合間を縫って片手間に従事していた者に過ぎないと認めるのが相当
平成19年1月18日裁決
労務は一時的ないし臨時的なものであってその年を通じて6月を超えるとは認められない。
平成15年3月25日裁決
請求人の妻である医師は、事業に専ら従事した期間は週1日のみであり事業専従者に該当しない。
つまり もっぱら従事するは条文にもある通り従事する期間つまり量的な時間が要件であると思われる。
白色申告者の定額控除の額は昭和36年の創設時、農業の平均労働日数を全国平均で151日とし、専ら従事した期間について年間151日の労働が 1年を通じて6ヶ月を超える期間従事したものとしている。
ちなみに1年のうち日曜祭日を除いた日数はおよそ220日である。
平成7年の白色申告者の定額控除額は86万円だがこれは時給800円とすれば1075時間に相当し1日7時間とすると 153日の労働となる 。
しかし、たとえ会計事務所においてコンピューター関係、経理、所長代理として一日6時時間事業に従事していたとしても事業に専ら従事しているとはいえず、青色事業専従者には該当しないとした事例がある。
平26-02-0裁決
税理士が、その妻に支払った青色事業専従者給与
平成21年675万、22年572万、23年530万を青色事業専従者給与として必要経費に算入
税理士の妻乙は法人3社の役員として法人の業務に従事しており役員報酬の合計額は平成21年960万 平成22年920万 平成23年960万
A社は不動産賃貸借管理業 乙は代表取締役で且つ宅建主任者 売上 5000万 社員5,6名。
B社は経営コンサルタント業を営み 乙は取締役で売上約1500万円
丙社は建築コンサルタント業で乙は取締役 売上1200万円アルバイト3名
裁決では
妻乙が法人3社(各関連法人)の業務に従事している場所や時間帯は、税理士業(本件事業)の業務遂行の場所及び時間帯と一致しており、また、乙自身が、本件事業の業務と各関連法人の業務の従事時間を区分することはできず、従事する時間帯も明確に区分できないことを答述していることからすると、乙は、本件事業の業務と各関連法人の業務を間的空間的に区別することなく、同時並行で随時行っていたものと認められる。
全くの名目取締役であればともかく、名実ともに取締役として職務を遂行し、その対価を得ている者は、常時、取締役としての責任を負って、会社のあらゆる業務について指揮、監督し得る状態にある必要があり、常に本件各関連法人の取締役として業務を遂行し得る状態にある以上、本件各関連法人の具体的な業務をしていない時間があったとしても、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」当たらず事業に専ら従事しているとはいえず、青色事業専従者には該当しない。
地裁では「他に職業を有する者」である期間は、原則として事業専従期間に含まず、それらの者のうち「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」を例外的に除くものとするそして、例外に該当するかどうかは、他の職業に従事する時間がおよそ短く、当該事業に専ら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうか、さらには、当該事業及び他の職業の性質、内容、従事する態様その他の諸事情に照らし、実質的にみて事業に専ら従事することが妨げられないかどうかによって判断するのが相当であるとした。
そのうえで税理士側の当初の聴取書に記載された乙の従事時間
税理士事務所 6時間
A社3時間
B社1~2時間
C社1~2時間 の申し立ては十分信用できるとし、乙はA社の代表取締役、B社及びC社の取締役として、関連会社の業務に従事していたのであって、「他に職業を有する者」であったことは明らかであるから、事業に専ら従事しているとはいえず、青色事業専従者には該当しないとした。
高裁も同様の理由で納税者敗訴
つまりこの判例では、専従とは、事業に時間的な従事をしていたとしても他に従事する時間が短く、当該事業の性質、内容、従事する態様等に照らし、実質的に事業に専ら従事することが妨げられていないことがその要件であるし、文字通り「せんじゅう者」として厳格に「専従」を要件としている。
当事例の場合
おばちゃんが名目的もしくは非常勤役員の場合、団子屋の仕事に専ら従事することが妨げられないため事業専従者の要件に該当する。
おばちゃんが名実ともに取締役として職務を遂行しその業務が製造と販売が同じ場所で行われ、その遂行の場所と時間を区分できず同時並行で行っているとすると、役員報酬の額からしても専ら従事することが妨げられないことが明らかであるとはいえず専ら事業に専従しているとは言えない。
役員報酬が無報酬であっても取締役として法人業務に常時従事していれば他に職業を有する者に該当し青色事業専従者には該当しないが、実務上の判断要素として役員報酬を支給の大小も判定要素とされると思われるため、青色事業専従者としての給与支給をするのであれば役員報酬はあくまで非常勤役員としての最低限の報酬にすべきである。
所得税の57条がある以上その辺のバランスを考慮した給与、報酬の決定が必要と思われる。
本音を言うと
足し算仕事を前提とした所得税第57条の「取締役が青色事業専従者をしているとその要件を欠く」という考え方はもう時代にそぐわない
白色事業専従者控除が始まったのは昭和36年で青色事業専従者控除が始まったのは昭和47年である。
算定根拠に昭和36年の農村地域の平均給与を斟酌していることから当時質的な労働は全く考慮せず 単純労働を想定している。
税理士が、妻乙に支払った青色事業専従者給与判決は、会社の常勤役員なのだから24時間365日役員として責任がある。
だから他に職業を有するので専従者ではないとの判断であるが現実に税理士の妻乙は片手間でも一時的でも臨時的でもなく税理士業務に従事している。
つまり裁判所は役員の責任という目に見えない質的要素を用いる一方でそれを量的要件に変換し専従者の要件に該当しないとしている。
所得税第57条の立法趣旨は個人事業者の恣意的な家族分配による税負担軽減を防止するため( 平成16年11月2日最高裁判決)のものであることを考えると税理士が妻に払った青色事業専従者給与が恣意的な家族分配による税負担軽減行為とまで言えず、青色事業専従者給与を全額否認することはかえって税負担の公平を損なう判断だといえる。
この事例だと妻乙は法人の常勤役員あると夫の事業を手伝っていても離婚でもしない限り未来永劫青色事業専従者給与が必要経費に算入できないことになる。
現在は事業の内容が多様化しており青色事業専従者給与と生計別親族に支払う給与を区分けしなくてもよい場合があるのではないかと思われる。