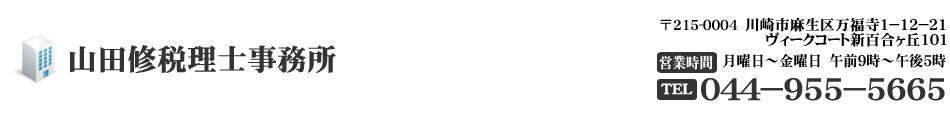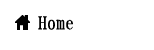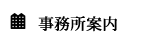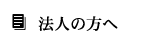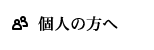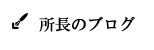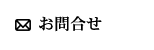個人の方へ
法人成り
個人事業主、節税改
事例研究
所得税税法上 もくろみ、慣行及び嗜好として負担した支出(家事関連費)と必要経費の範囲について
専有部分の形状、床面積等が契約時のそれと異なったことによる迷惑料の所得の区分
譲渡所得の計算上、相続により取得した借地権の瑕疵について支払った和解金及び弁護士費用について取得原価算入の可否
借地法上の『借地権』の存否 借地契約(賃貸借契約)期間満了前に借地上の建物が滅失した場合の借地権の有無
本年8月Aは贈与者甲から土地(以下『本件土地』という)の贈与を受けた。本件土地に関しての経緯は下記のとおり。
(1) 贈与者甲は、今から30年前に本件土地を更地(空閑地)の状態で取得した。
(2) 贈与者甲は、上記(1)に係る本件土地の取得後、直ちに、甲㈱(贈与者甲が主宰する同族会社)に対して、有償契約により本件土地を貸し付けた。
① 建物の所有を目的とする賃貸借契約で、借地法(平成4年8月1日廃止)に規定する借地権が設定されたものと認められる。
② 相当の地代のような高額な地代ではないが、賃貸借契約と認められる地代の支払があった。
③ 土地の賃貸借に対して、権利金等の名目による一時金の支払いは認められない。
④ 本件土地の賃貸借契約に関して『土地の無償返還に関する届出書』が納税地の所轄税務署長に提出していない。
(3) 上記の(2)の契約に従って、本件土地の賃貸借契約締結直後に、甲㈱は、本件土地上に立体駐車場(堅固な建物と認められる)を建築した。
(4) 12年前に、駐車場内で事故が多発したため同建物を取り壊した。
(5) その後においても、甲㈱は贈与者甲に対して、従来どおりの地代の支払いを継続している。甲㈱は、本件土地を自社の資材置場及び駐車場として利用している。(建物の新たな建築はしていない)。
上記のような状況下において行われた本件土地の贈与について、受贈者の贈与税が課税価格に算入すべき本件土地の価額はいくらか。
〔必要資料〕
1. 自用地として本件土地の相続税評価額・・・1億円
2. 借地権割合 ・・・60%
回答
土地の更地価額から借地権価額を控除した1億円×(1-0.6)=4千万円が課税価額となる。
思考過程
借地権とは
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を借地権という。
「建物の所有を目的とする」とは、借地人の借地使用の主たる目的がその土地に建物を築造し所有することにある場合を意味し、借地人がその土地に建物を築造・所有する場合であっても、それが借地使用の従たる目的であるときは、建物の所有を目的とするということはできず、借地借家法の適用はない。このことから、借地使用の主たる目的が建物の築造・所有にあるときは、当該建物が住居・店舗・事務所・倉庫・工場などの独立性のある建造物であれば、その用途を問わないとされている。たとえば自動車教習所は借地権あり、バッティングセンターは不可という判例あり。
平成4年7月31日以前に設定された借地については、その存続期間や更新期間は廃止された借地法(旧借地法)が適用される。
契約で期間を決めていない場合には、堅固な建物(ビルなど)を建てる場合には60年、非堅固な建物(木造建物など)を建てる場合には30年となる。
契約で期間を決めた場合でも、法律で最短期間が強制され堅固な建物を建てる場合には契約期間は30年以上、非堅固な建物を建てる場合には20年以上となる。
これよりも短い期間を定めた場合、その期間の定めは無効となり、契約期間を定めなかったことになる。つまり原則に戻り60年(堅固建物)か30年(非堅固建物)となる。
次に、更新した場合の期間だが、堅固建物は30年。非堅固建物は20年となる。
では、建物が滅失した場合借地権はどうなるのだろうか?
滅失とは、地震や風水害などの天災や改築のための取り壊しのような人為的な消滅をいう。
朽廃とは、人工的でなく自然的な腐食状態により社会的経済的効用を失った場合をいう。具体的には建物の土台や柱などが破損し、壁等が剥落し、材料が腐食している場合にその程度いかんによって判断される。
旧借地法で借地契約が終了するのは朽廃で滅失では,契約終了にならない。
借地法7条では,建物の滅失について『再築を認める』ことが前提となっている。
「借地上の建物が滅失し、借地権者が新たに建物を建造するに当たり、土地所有者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨借地権者をして特約させた場合にも右特約は借地法11条により無効である。※最高裁昭和33年1月23日」
上記のことから、30年前贈与者甲は甲㈱と建物の所有を目的とする賃借契約を結び、その土地の上に堅固な建物を建築した為、借地権の存続期間は60年となる。
また立体駐車場の取壊しは朽廃とはならず借地権失効の要件とはならない。また甲㈱は地代の支払を継続しており借地権が存在することは明らかであるといえる。