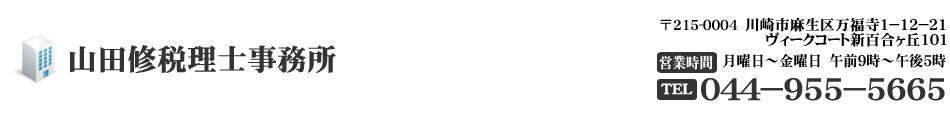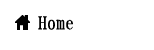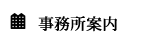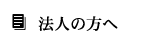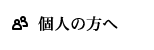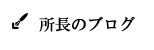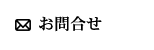個人の方へ
法人成り
個人事業主、節税改
事例研究
所得税税法上 もくろみ、慣行及び嗜好として負担した支出(家事関連費)と必要経費の範囲について
専有部分の形状、床面積等が契約時のそれと異なったことによる迷惑料の所得の区分
譲渡所得の計算上、相続により取得した借地権の瑕疵について支払った和解金及び弁護士費用について取得原価算入の可否
所得税税法上 もくろみ、慣行及び嗜好として負担した支出(家事関連費)と必要経費の範囲について
平成27年11月7日
< 必要経費の考え方 >
所得税法では必要経費について法37条で「その年分の事業所得の金額
~中略~
の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額
を得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」としている。
昭和38年の税制調査会ではその答申において、できるだけ広く経費損失を考慮すべしという考え方と家事費と区分困難な経費は排除するという広狭2つの考え方があることを指摘し、事業経費についてはできる限り前者の考えを取り入れることが望ましいとしている。
つまり事業所得について言えば、所得税法37条は、法人税の損金と同じ内容となっているが所法45条(家事関連費の必要経費不算入等)で必要経費の範囲を制限している。
所法45条を要約すると、次のようになる。
家事費は必要経費に算入しない。
家事関連費は業務の遂行上必要(必要な部分が50%超かで判断~所基通45-2)であり、かつ明らかに区分できる金額を必要経費に算入する。としている。
ところで家事費とは、金子宏教授によると衣服費・食費・住居費・娯楽費・教養費などのように、個人の消費生活の費用のことをさし家事関連費は、接待費、交際費などにその例が多いが、必要経費と家事費を併有している費用をいう。
つまり、家事関連費の中には、必要経費になるものとならないものがあり、その区分けの基準は、業務の遂行上必要かつ明らかに区分できるものかで判断するとしている。
法人税では、原則事業遂行上の支出を損金としているのに対し、所得税では家事関係費について上記の制約がある。
(1)業務の遂行上必要であるとは
その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用について、業務に関連して支出されるすべてのものなのか、業務遂行上不可決な支出か、今までの判例学説では業務との直接的な関連性が要求されるとしている。
碓井光明教授によると
「法37条のみに即して言えば、業務について生した費用であれば良いように見えるか、施行令の規定によれば業務の遂行上必要であることが要求される。業務とわずかな関係があるだけでは必要経費とは言えない。業務での直接的な関連性が必要であると明言されていないが、強い結びつきを要求している。」
裁決及び判例を検討すると「客観的にみて業務と直接関連をもち且つ業務の遂行上通常必要な支出」と判示(青森地裁昭和60年11月5日)している。
つまり直接性、通常性(東京高裁H18.3.16)、必要性、客観性の4つが必要で、逆にこれらに該当しないものは家事費とされる。
所得税法では、必要経費かそうでない支出かこの2つの区分しかないことになる。
裁決判例を見ると販売費一般管理費その他所得を生ずべき業務により生じた費用の検討を十分にせず、私的な支出の可能性が少しでもあると家事関連費に分類し、業務との直接性と金額の明確性が不十分だと言って必要経費を否認している事例が多い。
結局のところ納税者が販売費一般管理費であると認識し申告しても課税庁側が必要経費に算入できないと認定すればそれは家事費となってしまうのである。
回答事例
1 春夏用の背服2着14万円
平成24年度税制改正において給与所得者の特定支出控除について見直しがなされ、勤務必要経費として「衣服費」が含まれることとなった。
具体的には、制服、事務服、作業服および給与等に支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服が該当する。
スーツについては、国税庁が公表した平成24年9月12日(情報)質疑応答事例の中で、以下のように示されている。
「・・勤務場所においては背広などの特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けているときや、勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広など特定の衣服を購入するための支出は、特定支出となります。
また、背広については、出勤・退勤の途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所において背広を着用することが求められており、その背広の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものについては、特定支出となります」
これはあくまで給与所得者の特定支出の範囲についての解釈であるが、個人事業者の必要経費の解釈についても当然に準用できるものと考えられる。
即ち、スーツ代については、出勤・退勤の途上や他用で着用する場合があるとしても、職務場所においてス-ツを着用することが求められており、そのスーツの購入がその者の職務の遂行に直接必要なものであり、社会通念の範囲内であれば、必要経費として算入することができると考えられる。
2 ライオンズクラブの会費28万円
一般的にロータリ-クラブの方がラインズクラブより入会審査が厳しいとされる為、当事例はロータリ-クラブの裁判事例を参考に検討する。
昭和58年1月27日や平成26年3月6日裁決ではロータリ-クラブの会費は主として業務の必要性に基づくものであるとは客観的に認められないとして必要経費算入を否認している。
平成17年4月26日裁決でも同様にロータリ-クラブはいずれも個人的立場に基づいて入会するもので事業との直接関連性を有し業務の遂行上必要なものでそれが客観的に認識できるものでなければならないとして必要経費算入を否認している。
●見解
入会の動機が、会の本来の趣旨とは別に顧客獲得のための入会であれば、本来の家事費ではない。
法人税法上では、交際費で損金不算入となり所得税法との課税上のバランスが取れているという考え方もあるが、交際費の損金不算入の制度の趣旨は企業の資本蓄積を促進するため、冗費を節約するための措置であり課税の趣旨が全く異なる。
事業を営む上で任意加入であるという理由から販売費一般管理費になるという検討もせず、家事関連費に分類し、そこに直接性や客観性に欠けるから、必要経費算入を否定するのはどうかと思われるが、現在の判例通説としては、家事費とされ必要経費とはならない。
3 クラウン4WDの減価償却費
車両の使用は事業の遂行上必要なものであり減価償却費はその年における販売費、一般管理費に該当し必要経費として認められる。
ただし、日曜祭日など私用で車を利用するときは合理的な按分が必要と思われる。
4 情報提供料と顧客譲受けの謝礼金について
~通常性、直接性は必要経費の算入要件か~
弁護士役員の交際費について東京高裁平成24年9月19日判決 最高裁棄却のため確定・・・条文上業務と直接関係を持つことは文理解釈上読みとれないとして直接性を要件からはずし、事業所得を生すべき業務に必要な支出は一般対応の必要経費に該当するとしている。
この理論構成は次の通り
弁護士の事業を生ずべき業務を行うためには弁護士会、日弁連の会員にならないと事業が営めない。
そして弁護士会の活動は、その社会的信頼の維持や業務の改善に資するものであるのでその業務に密接に関係する。
つまり人格の異なる弁護士会の役員活動は一般対応の必要経費に該当する。
個別事例では、弁護士会の役員としての酒食を伴う懇親会は、社会通念上業務の遂行上必要である。
二次会の費用は、業務上の必要性が含まれていたとしても旧交を温める、個人的な交際の側面もありその金額が明らかに区分できないから認められない。
執行部メンバー全員の宿泊費の負担については、弁護士会の公式行事とも社会一般の行事でもなく控訴人一人で全額負担しており、その額が過大であるとして否認。
また、役員に立候補した費用のうち不可欠なものは認めそれ以外は該当しないとしている。
同様に最高裁平成18年4月20日がある。
土地改良区の組合員が、改良区内の農地を転用目的で譲渡するにあたり、その改良区に支払った決済金・協力金が、その農地の譲渡費用に該当するかどうか争われた事案である。
この最高裁判決がでるまで判例は直接且つ通常必要な費用でなければ譲渡費用として認めないとしてことごとく法令の根拠なく直接性、通常性を必要経費の要件にし、踏襲してきた。
しかし、この最高裁判決は、いままでの判例を変更し、直接性、通常性が必要経費の要件ではないことを確認している。
「譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものである。しかしながら、所得税法上、抽象的に発生している資産の増加益そのものが課税の対象となっているわけではなく、原則として、資産の譲渡により実現した所得が課税の対象となっているものである。そうであるとすれば、資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項にいう譲渡費用に当たるかどうかは、一般的、抽象的に当該資産を譲渡するために当該費用が必要であるかどうかによって判断するのではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものである。」
この最高裁判決は、必要経費は通常且つ直接必要な経費でなければ必要経費として認めないとしてきた税実務、判例を覆し、客観的に必要な経費であれば、必要経費として認めるとした。
この必要経費の範囲を巡る考え方はなにも農地転用決済金等がある場合における譲渡費用にだけあてはまる考え方ではない。
所得税制の必要経費の範囲を考える上で全般的にあてはまる考え方であると思われる。
このようにみると必要経費の要件は、(通常性と直接性を除いた)所得を生ずべき業務について客観的に必要な支出であるといえる。
●見解
当事例の場合、その支出は衣食住、娯楽、教養費等の家事費とも言えず、税理士のBからの請求があったわけではないが、顧問先の紹介がなかったら支出しないものである。
法人税では、交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出ものをいう。
これを当事例に当てはめると取引の謝礼と情報提供料となり交際費に該当する。
交際費は、販売費一般管理費に属するため、この支出が所得を生ずべき業務について客観的に必要であったことの説明ができれば必要経費算入の可能性があると思われる。
では、客観的に必要とは、自己の計算と危険において独立して、営利性、を有し、かつ、反復継続して事業を行っている税理士が、顧問先紹介により生じた所得について紹介後の顧問先の過年度の税務処理の経緯、税務相談を受任した時の情報提供の内容及び同人との過去の付き合いなど総合勘案して、過分ない金額として支出した額が100万円であったという説明では、客観性は担保できないだろうか。
なお、取引の謝礼部分は、その支出の効果が1年以上に及ぶもので市場の開拓、新たな事業開始のため特別に支出した費用として繰延資産(開発費)として60か月で償却することも考えられる。
5 立替払した源泉税50万円
貸倒損失については別段の定め(第45条から57条他)がある。
法第51条2項において
居住者の営む 以下中略~
事業所得~を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の~事業所得の金額~金額の計算上、必要経費に算入する。としている。
しかし、裁判例を見る限り必要経費の条件は厳しいものとなっている。
津地方裁平成18年4月27日では・・・・
「税理士業を営む原告の関与先法人A会社に対する出資金については、そもそも出資金が
『売掛金、貸付金、前渡金その他これらの準ずる債権』
といえるかに疑問がある上、税理士業としての事業所得を得るために通常かつ必要なものと客観的に認めることはできず、また、同社に対する貸付金については、原告が関与先への貸付けをその業務に関連して通常一般に行っていたわけでもないから、事業所得を得るために通常かつ必要なものと客観的に認めることはできないため、その回収不能額を貸倒損失として必要経費に算入することはできない。」
としている。
又東京高裁平成18年3月16日判決でも 控訴人Xが顧客等に対して行った本件各貸付等が、客観的に見て、税理士業と直接関係を持ち、かつ、業務遂行上通常必要であるかについての判断は、単に事業主の主観的判断によるのではなく、当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に則して社会通念に従って実質的に行われるべきで、本件各貸付等の債務者のうち税理士業に係る顧問契約は、税理士法2条1項に定める業務のうち税務代理及び税務相談を対象とするものであって、金銭の貸付けや債務保証は含まれていない。
そうすると、Xの税理士業において、社会通念に照らして、顧問先等に対して金銭の貸付けや債務保証を行うことが税理士業務と直接関係を持ち、かつ、業務遂行上通常必要なものであるということもできないから、本件各貸付等が、客観的に見て、Xの税理士業務と直接関係を持ち、かつ、業務遂行上通常必要なものであるということはできないため、本件各貸付等に係る損失額を必要経費に算入することはできない。とし必要経費算入を否定している。
●見解
これを当事例にあてはめると、元々C社とは文書による顧問契約を交わしておらず、その業務内容は現実にC社に対して行っていた役務提供すべてである解される。
源泉税の立替は当時1月10日が納期限であり、会社側が納付を失念した時の加算税賦課を回避する為、税理士業務の一環として行っていた。
実態は司法書士が登記の際、登録免許税を立替え手数料と一緒に請求することと同様の行為といえる。
このように考えるとこの立替金は事業の遂行上生じた前渡し金その他これらに準ずる債権であるといえその貸倒は必要経費に該当すると思われる。
まとめ
税法の本を読むと、個人は所得活動の主体であると同時に衣食住など消費支出の主体であるのでその中間のグレー部分が必ず発生しそれを家事関連費と呼ぶ。そして業務の遂行上必要で明らかに区分できる金額を必要経費に算入するとしている。
この事例発表にためにいくつかの裁決例や判例及び論文を読んでみた。
裁判に提起するほとんどの納税者が恐らく思っていたることは法人なら認められる支出ではないかということである。
つまり、必要経費に計上した納税者は、業務の遂行上必要であったという認識の上に支出しているのである。
その訴えに対して裁判所は、直接性、通常性、必要性、客観性という盾を使ってことごとくその主張を退けている。
その本質にあるものは、事業の主体が個人であるからだと思われる。
つまり、支出をするのも本人、記帳も本人か配偶者で法人のように複数の人のチェックを受けるシステムとなっていない。
つまり、支出に客観性が担保されていない。
その上、会計や税法の知識に乏しい人が多く借入金の返済を経費としたり、減価償却について取得時期や残存価額の記載を失念し何十年も償却計算を行っているという事例も散見される。
そのような所得税の納税義務者の主張を無制限に認めたくないという意図があるように思える。
しかし、事業所得を自己の計算と危険において独立して、営利性、を有し、かつ、反復継続して行うものと定義しておきながら、個人はいい加減だからという理由で必要経費の範囲を制限するのは、法人と比べ課税上不平等と言わざる得ない。